二次創作保護
同人誌即売会を中心とした二次創作文化は、かつてTPPの「著作権の非親告罪化」により存続の危機に陥りました。しかし二次創作文化はクリエイターの卵を産み育てる「創作のゆりかご」であり、漫画界の発展の大きな力となっています。私は誰もが尊重し合い創作できる文化とあらゆる創作者を引き続き守っていきます。
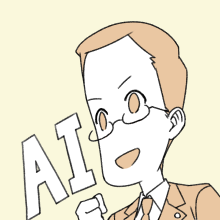
BASIC POLICY BASIC POLICY
同人誌即売会を中心とした二次創作文化は、かつてTPPの「著作権の非親告罪化」により存続の危機に陥りました。しかし二次創作文化はクリエイターの卵を産み育てる「創作のゆりかご」であり、漫画界の発展の大きな力となっています。私は誰もが尊重し合い創作できる文化とあらゆる創作者を引き続き守っていきます。

現在、映画やアニメ、ゲーム、マンガなどの日本コンテンツが海賊版のターゲットとなり、創作者は不当に利益を搾取されています。年間被害額は兆単位にのぼり、コンテンツ産業の発展を大きく妨げています。関係者の努力により海賊版の駆逐は進んできましたが、官民連携による摘発、特に海外の海賊版サイト運営者への国際執行や、正規版への誘導、啓発活動などの取り組みなど、今後も状況に応じた対策を続けていきます。
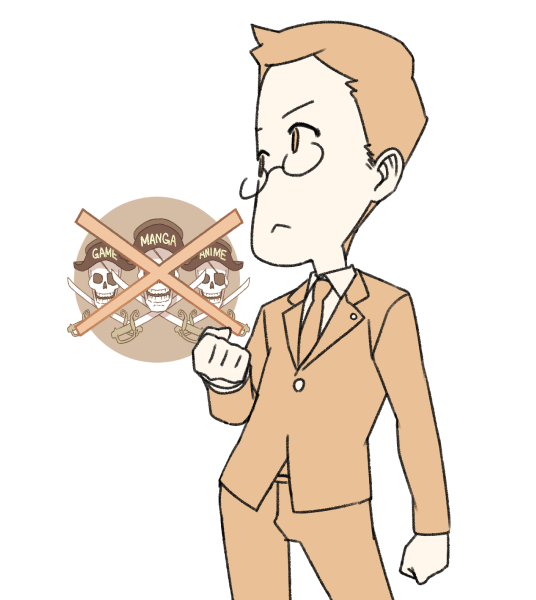
児童ポルノ禁止法は、改正のたびに「児童ポルノの中に創作物を含めるか」が議論されています。法律の本来の目的は、実在する被害者のいない架空の創作物ではなく、現実に被害を受ける子どもたちの救済であるべきです。このような必要性のない規制に反対します。
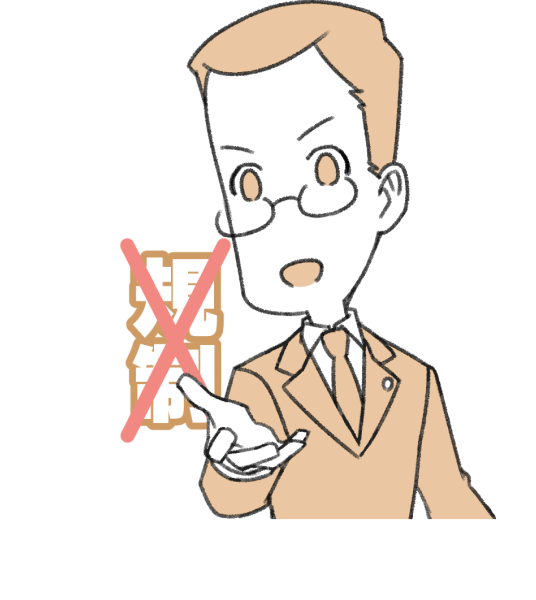
国連をはじめとする欧米団体が一部の偏った意見を採用し、日本の創作物に対して、実態を正しく反映していない見当違いな勧告をすることがあります。そうした偏った考え方、誤解や曲解に基づく海外からの規制圧力からクリエイターや創作物を守るとともに、引き続き適切な説明や反論を行なっていきます。

ソフトウエアやインターネットサービスなどのプラットフォーマーの多くは欧米のものです。これらが独自の基準で日本の創作物への根拠なき一方的な検閲・規制を行わないよう、引き続き反対していきます。
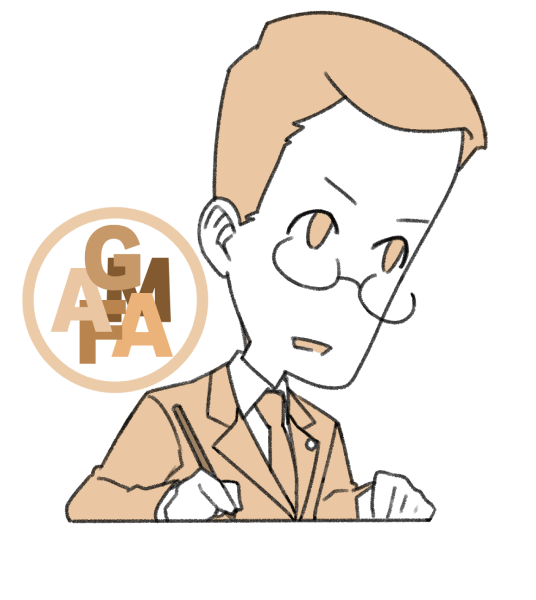
SNSでの誹謗中傷防止対策のひとつとして、ブロッキングが議論に上がることがあります。しかしこれはプロバイダーによる検閲に繋がる危険性があり、通信の秘密を保障する憲法に違反します。違法サイトは看過できませんが、「著作権者を守るため」との建前のブロッキング法案に反対します。
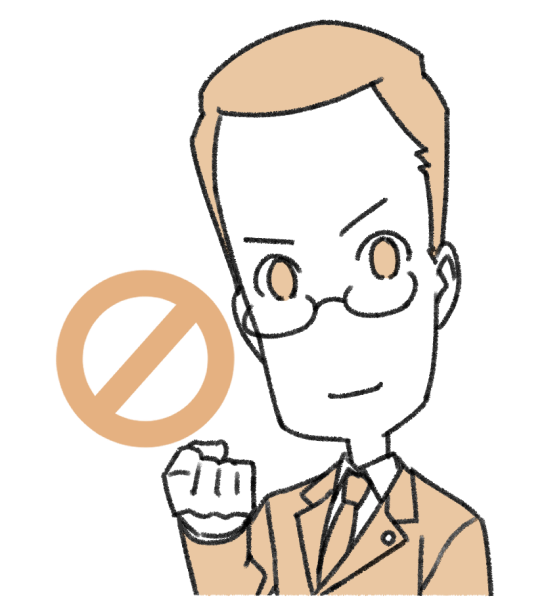
現在日本のコンテンツ産業に大きな打撃を与えている海賊版に対し、違法であるという認識がない利用者が多いことがわかっています。小中学生のうちから著作権について教育を進めることで、海賊版の撲滅を目指します。また、ネットリテラシー教育により、子どもの才能や生活の安全を確保します。

RELATED POSTRELATED POST